ハロウィーンのお祝いにまつわる規制が緩和され、日本各地でパレードやパーティーが今年は開催され、久々に盛り上がったと報道されている。そもそもなぜ日本でこれほどまでに普及したのか?と考えると少し不思議だが、きっとコマーシャルな理由なのだろう。ハロウィーンのお祭りに参加しようとすると、コスチューム、メイク、飾りつけ、菓子など、買うものが多い。
米国では、日本以上にハロウィーンは大きなイベントだが(こちらは国の歴史を考えるともっともだ)、ラティーノ人口の増加が激しい米国では、「死者の日」(el Dia de los Muerto / The Day of the Dead)のお祝いも、以前に比べ知名度を上げている(もとよりラティーノが多い米国南西部、フロリダ、ニューヨークなどでは随分と前から盛んだった)。時期がほぼ同じ2つのイベントだから、「死者の日」(死者の日は、地域差があるが10月終わりから11月の第1週に催される)と「ハロウィーン」は混同されがちである。骸骨や幽霊のような人物を模した仮装など、その「一見、怖い感じ」も共通する。ラテンアメリカ出身者以外の人にとって、「ラティーノたちのハロウィーンの祝い方」と、死者の日は誤解されることが多い。実際、死者の日に見かける骸骨や死んだ人のような仮装は怖がらせるためではなく、「あの世の住人たち」(有名人だったり、親戚のおじさんだったり)を表しており、この世の住人たちとの再会を祝するムードを高める仕掛けだったりする。
もとより「死者の日」は、ラテンアメリカやカリブ海島嶼で幅広く祝われてきた。とはいえ断然、メキシコの「死者の日」は有名だ。
この時期にラティーノについてお話させていただく機会がある時は、映画『リメンバーミー(原題“COCO”)』 (2017)の話をすることにしている。先日またこの映画を観た。ピクサー製作のディズニー映画だが、いわゆる「マイノリティ」の文化をテーマにした作品にしては珍しく当事者メキシコ人やメキシコ系の間でも評価がよい作品らしい。
音楽が禁止されている家に生まれたのに、音楽が大好きな主人公の男の子ミゲル。こっそりと楽しんでいたギターが家族に見つかり、一切の音楽を禁止されたミゲルは家を飛び出す。そして、いつの間にか死んだ人びとの世界に迷い込む…。すべてが「死者の日」の出来事。キラキラした死者の世界が眩しい。
「死者の日」には、あちらの世界から死者たちがこちらの世界にやってくる(日本のお盆と似ている)。生きている家族たちは、家族に会いにくる「亡き人たち」の道しるべとなるマリーゴールドの花をいたるところに飾る。墓場には人びとが集まり、亡き人たちの大好だった食べ物を備え、歌を歌ったり踊ったりしてとても楽しそう。
年に一度だけ、あちらの世界とこちらの世界にマリーゴールドが敷き詰められた橋がかかり、あちらの世界から家族に忘れられていない住人だけが橋の通行を許可される。生きているものたちの世界で自分を覚えている人が誰もいなくなったら、「あちらの世界」でその姿は消滅する(その後、どこに行くのか?は不明)。原題は、主人公ミゲルのひいお婆さんの名前にちなんで、COCO。高齢で意識も朦朧としているCOCOに、ミゲルは「死者の世界」で聴いたCOCOのお父さん曲「リメンバー・ミー」を歌う。 この曲は、Migel(ロサンジェルス出身のR&Bシンガー)とNatalia Lafourcadeのデュエットのバージョンがいい。映像のなかの祭壇(オフレンダ)もよい。(DisneyMusicVEVO)。https://www.youtube.com/watch?v=E7VPdpEV1m0
映画では家族愛、忘れずに亡くなった人のことを語り続ける大切さが伝えられている。画家のフリーダ・カーロ、伝説のプロレスラーのエル・サント、マリアッチ、メキシコの村の風景、大家族、タップダンス、伝統音楽などメキシコっぽいものがたくさん映画の中に散りばめられている。エッジの効いたフリーダは死者の世界でも健在。メキシコ版「あちらの世界」の人間臭さや欲望は「こちらの世界」に引けを取らない。スペイン語の歌詞やセリフがそのまま使われ、英語に訳されていない部分も多いと思った。もはやこれくらいのスペイン語は米国人なら理解できる、という判断か。確かにアメリカ英語にスペイン語の語彙はかなり増えてきている。米国のメキシコ系家庭では、幼い子どもたちにメキシコの伝統を学んでもらおうと教育的な配慮からこの映画を見せることもありそうだ。ポピュラーカルチャー映画を通して意識されるようになる民族的なアイデンティティはかなり影響力がありそうだ。
前にも、「死者の日」について書いてました。https://mikamiyoshi.com/7/
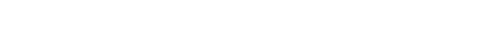



コメント